遺言書の内容に納得いかない。
自分の相続分が極端に少ない。
そんな時は遺留分を侵害されている可能性があります。
今回は、遺留分減殺請求を自分行う方法について解説していきます。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求とは自分の遺留分を請求する行為をいいます。
遺留分とは法定相続人が最低限取得できる財産のことです。例えば、遺言書で特定の人物にすべての財産を相続させるとあった場合、他の相続人は一切の財産を受け取ることができません。しかし、これでは生活に困窮する相続人が出てしまったり、問題が発生します。そこで、相続人が最低限取得できる遺留分というものを認めているのです。
遺留分は何もしなくても認められるというものではなく、遺留分を請求する必要があります。この遺留分を請求する行為のことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求の方法は裁判手続きによる請求と裁判外による請求があります。
裁判手続きによる請求は遺留分減殺調停(遺留分減殺による物件返還調停)となります。遺留分に関する事件は調停前置主義といって、いきなり訴訟を提起することはできず、調停をしなければなりません。
次に裁判外による請求ですが、これは相手方に直接、請求の通知をすることをいいます。
通知の方法は特に定めはなく、口頭でも有効です。しかし、時効の関係上、証拠保全のために配達証明付きの内容証明郵便で送付するのが一般的です。
【文面の例】
○○ ○○ 殿
平成○○年〇月〇日
○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○ ○○ ㊞
遺留分減殺請求書
私は○○○○(被相続人)がその遺産の全てを次男である貴殿に相続させる旨の遺言書を残していたことを、平成○○年〇月〇日に知りました。
同遺言書の内容は、私の遺留分を侵害するものといえますので、私は本書をもって、貴殿に対し遺留分減殺請求をいたします。
以上
遺留分減殺請求書には、遺留分を侵害されたことと、遺留分減殺請求権を行使することを記載します。
このように、遺留分減殺請求の方法には2通りありますが、通常は裁判外による請求、つまり相手方に請求を通知して交渉することになるでしょう。まずは直接、相手方に請求して、話し合いがまとまらなかった場合は裁判手続きによる請求へと移行することになります。
遺留分減殺請求の方法として、まず最初に気を付けなければならないのは、遺留分が本当に侵害されているかを確認することです。
計算の間違いや勘違いもありますので、きちんと確認しましょう。
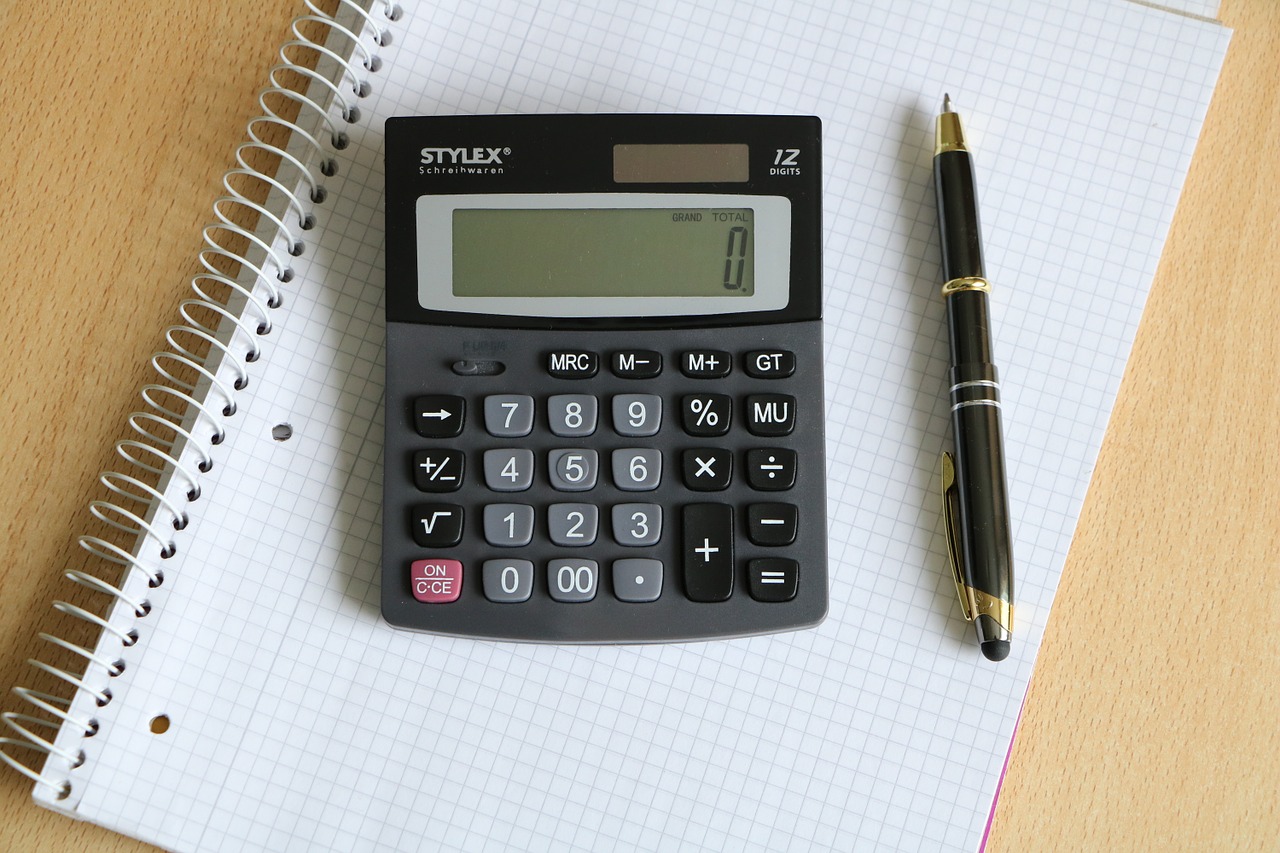
ちなみに、他の遺留分権利者が遺留分を放棄しても自分の遺留分は増えません。
遺留分減殺請求の順序
遺留分減殺請求は誰にしても良いというわけではなく、順序が定められています。
- 遺贈
- 死因贈与
- 生前贈与
遺贈、贈与が複数あるときは、まず遺贈から減殺し、次に贈与が減殺されます。
遺贈が複数ある場合には、遺留分権利者は減殺の対象財産を選ぶことはできません。遺贈全体の価額の割合に応じて減殺されることになります。しかし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
減殺すべき贈与が複数あるときは、新しい贈与から順に減殺します。ただし死因贈与があった場合は、死因贈与を最初に減殺します。
遺留分減殺請求の時効
遺留分減殺請求は、いつまでもできるものではなく、時効が定められています。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
上記のように、遺留分減殺請求は「相続の開始を知った時」と「減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないと時効により消滅します。つまり、これらの事情を知らなければ1年経過しても時効にはありません。
しかし、相続開始から10年経過すると、事情を知っているか否かに関わらず、時効となります。
遺留分減殺請求は誰が誰にするものなのか
遺留分減殺請求は遺留分を侵害された者が、遺留分減殺請求の対象となる行為によって利益を得た者に請求します。
【事例】
被相続人A、相続人BとCの場合
遺言者(被相続人)Aが相続人Bに対して全ての財産を相続させる内容の遺言書を残したとします。
この場合、相続人Cは遺留分を侵害されているので、相続人Bに対して遺留分減殺請求をすることになります。
また、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者にも遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求の解決までの流れ
遺留分減殺請求の解決までの流れは大まかにいうと以下の通りです。
- 遺言書の確認
- 相続人や相続財産の調査
- 遺産確認の訴え
- 遺留分減殺請求の通知
- 交渉
- 合意書や和解書の取り交わし
- 遺留分減殺調停
- 遺留分減殺請求訴訟
遺言書の確認
まずは遺留分減殺請求をする前提として、遺留分がどれほどあるのかを確認します。
そのために遺言書などの内容を確認しましょう。
相続人や相続財産の調査
次に相続人と相続財産のを調べます。
相続人を調べるのは、誰が相続人となり、何人相続人がいるのかを確認するためです。これにより遺留分が変わってきます。相続財産についても同様で、相続財産の全容を把握していないと、そもそも遺留分を侵害されているのか、どの程度の遺留分があるのかがわからないからです。
相続財産に加算される贈与は以下のものが該当します。
①相続開始前1年以内に贈与された財産の価額
②相続開始前1年以上前に、遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与。
③特別受益に該当する贈与
もっとも、遺留分遺留分額の算定が困難な場合は、まず遺留分減殺請求の通知だけ行っておくという方法もあります。
遺産確認の訴え
財産が相続財産にあたるのかどうかという問題が発生する可能性もあります。
そのため、遺産確認の訴えを提起するという方法もあります。
話し合いで決めることができれば良いのですが、相続財産にあたるかどうかについて争いがある場合、遺留分を確定することができません。そこで、遺産確認の訴えを提起して、遺産であることをはっきりさせておく必要があります。
遺留分減殺請求の通知
遺留分減殺請求の方法としては裁判手続きによる請求と裁判外による請求の2つの方法があります。
通常は裁判外による請求で、遺留分減殺請求を相手方に通知することになります。通知は念のため、配達証明付きの内容証明郵便にて送付しましょう。
交渉
遺留分減殺請求を相手方に通知後は、相手方と交渉することになります。
ここで話し合いがまとまれば、内容を書面にし、合意書や和解書として残しておきましょう。証明力や執行力を有する公正証書にしておくと、より安心です。
遺留分減殺調停
相手方と話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きによる請求の方法もあります。
具体的には、遺留分減殺調停を家庭裁判所に申立てします。申立ては原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
申立てが受理されると、申立人と相手方、裁判官又は裁判所が選任した調停委員の3者で話し合います。調停がまとまれば、執行力を有する調停調書が作成されます。
遺留分減殺請求訴訟
遺留分減殺調停でも話し合いがまとまらない場合は、訴訟という方法もあります。
遺留分減殺請求の訴訟は家庭裁判所ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴状を提出します。地方裁判所と簡易裁判所の違いは請求金額で、原則として請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所に提起します。140万円以下の請求金額の場合は、簡易裁判所に提起します。
遺留分減殺請求は弁護士に依頼する方法もある
遺留分減殺請求は通知自体はそれほど難しいものではありません。
しかし、話し合いがまとまらない場合は調停、訴訟と発展していく可能性もあり、手続きが難しくなっていくことも考えられます。そのため、自分で手に負えないような場合は、弁護士に依頼する方法もあります。
特に紛争性が高いと思われるような場合は、早い段階で弁護士に相談するのが良いかもしれません。
また、交渉が苦手だという人や、相手方と交渉するのは避けたいという人も弁護士に代理人として代わりに交渉してもらう方法もあります。

コメント